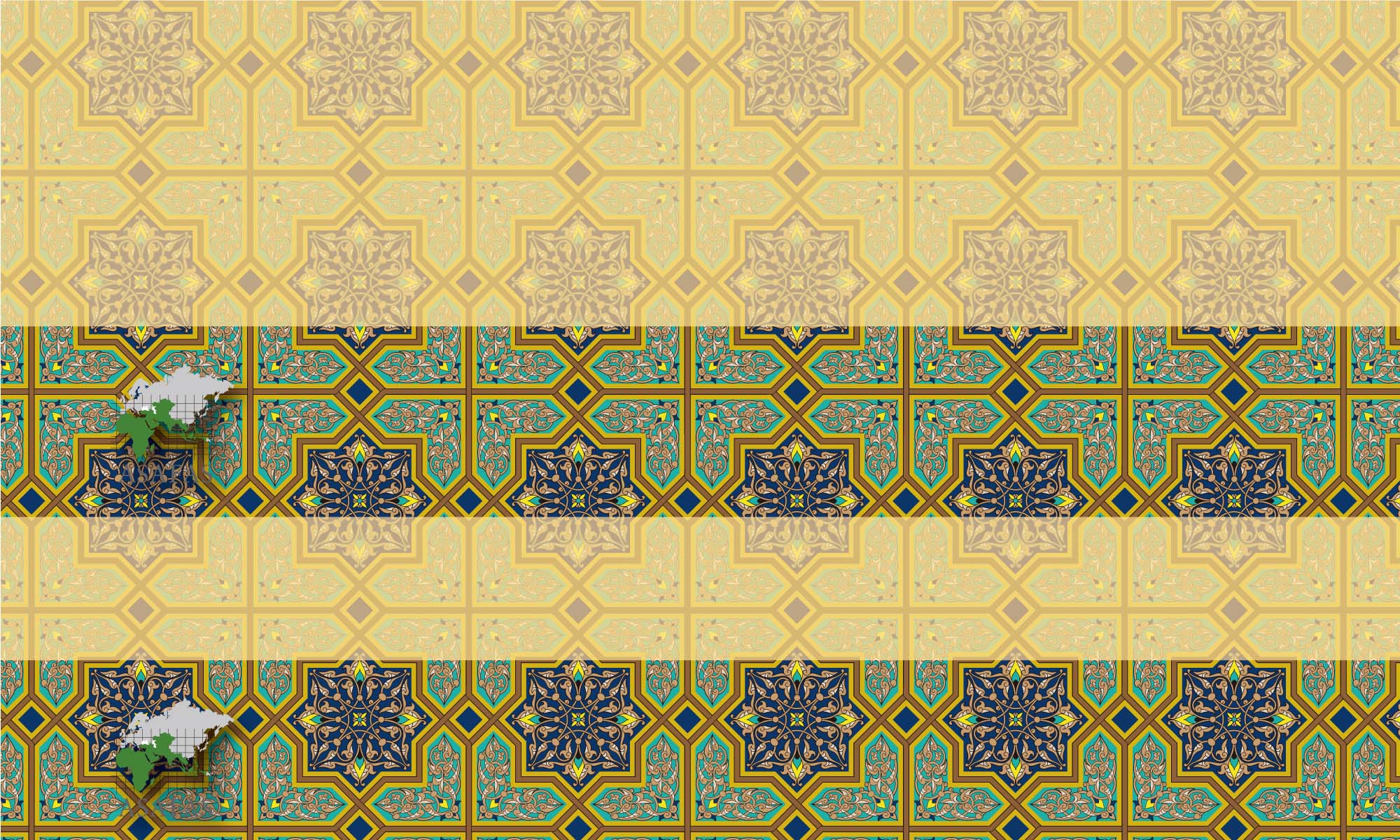2024年度第1回スーフィズム・聖者信仰研究会
【日時】6月9日(日)午後1~5時
【場所】上智大学6号館2-615a(対面およびZoomによるハイフレックス実施)
【報告1】本間流星(京都大学)「南アジア型イブン・アラビー学派の構築:アシュラフ・アリー・ターナヴィーの存在一性論を中心に」
本発表は、英領インド期の著名な学者であり、イブン・アラビー学派に連なるスーフィーでもあるアシュラフ・アリー・ターナヴィー(Ashraf ‘Alī Thānavī, d. 1943)の思想を読み解くことで、ターナヴィーがイブン・アラビー学派の地域的・時代的特徴をどのように体現し、同学派の知的伝統に如何なる貢献を果たしたのかを論じるものである。ターナヴィーは、南アジアの存在一性論を伝統的に特徴付けてきた「一切は彼なり(hama ūst)」の立場を継承することで、遍在的な神観念を軸とする存在一性論の理解を示したのみならず、その思想をハディースの注釈を通じて表現することで、存在一性論とイスラームの規範的伝統の調和をも図った。また、近代南アジアではウルドゥー語がムスリムの象徴的言語として普及し、当時の宗派間論争や改革主義運動の文脈で頻繁に使用されていた。ターナヴィーもウルドゥー語による著述を重視したが、彼はそれを存在一性論のような形而上学的なコンテクストにおいても用いた先駆者であり、まさにウルドゥー語で存在一性論を論じるという新たな知的潮流を南アジアにおいて生み出したとも言える。以上のことから、ターナヴィーは南アジアにおける存在一性論の伝統を単に継承するのみならず、そこにシャリーアとの調和的要素を見出し、さらにはイブン・アラビー学派の知的伝統とウルドゥー語を結び付けるという仕方で、「近代南アジア」という時代的・地域的特性を反映させた新たな学派のあり方を創出したと結論付けることができる。
【報告2】小倉智史さん(東京外国語大学AA研)「アクバル版『ラグ・ヨーガヴァーシシュタ』ペルシア語訳の校訂中間報告」
『ラグ・ヨーガヴァーシシュタ』とは、中世後期に大きな影響力をもったヒンドゥー教の哲学文献である。『ラーマーヤナ』の主人公であるコーサラ国の王子ラーマと、賢人ヴァシシュタとの対話の中で数々の物語や寓話が紹介され、人が生前解脱を達成するための手段が考察される。この文献の内容はムガル皇族の関心を引き、サリーム皇子(後の第4代皇帝ジャハーンギール)、第3代皇帝アクバル、第5代皇帝シャー・ジャハーン(一説には第6代)の長男であるダーラー・シュコー皇子がそれぞれ『ラグ・ヨーガヴァーシシュタ』のペルシア語訳を編纂させた。これまでにサリーム版とダーラー・シュコー版のペルシア語訳の校訂本が出版されている。報告者は未校訂のアクバル版の校訂作業をトロント大学のPegah Shahbaz氏と進めており、本発表はその中間報告である。
アクバル版のペルシア語訳は1602年頃に編纂された。サリーム版が1597–98年に編纂されたことから、二つのペルシア語訳は数年の間に相次いで編纂されたことが明らかになる。折しもこの時期はアクバルとサリームの対立が顕在化しており、本発表では、報告者はラーマが最終的に生前解脱を果たすという『ラグ・ヨーガヴァーシシュタ』の内容が、ムガル皇帝の神性王権の主張に都合の良いものだったのではないかという推測をした。サリーム版とアクバル版はともに存在一性論に基づいて、サンスクリット原典のヴェーダーンタ思想を解釈している。しかし、ヴェーダーンタ思想の根本原理である梵を、存在一性論における何に対応させるかという点で、両者の解釈は異なっている。サリーム版は、自己顕現が始まる以前の絶対非限定存在と梵を対応させている。これに対して、アクバル版は第一の自己顕現を経た後の統合的一者に梵を位置付けている。このような原典の思想の解釈の違いが、それぞれの翻訳がなされた環境に由来するものなのではないかと、報告者は見解を述べた。