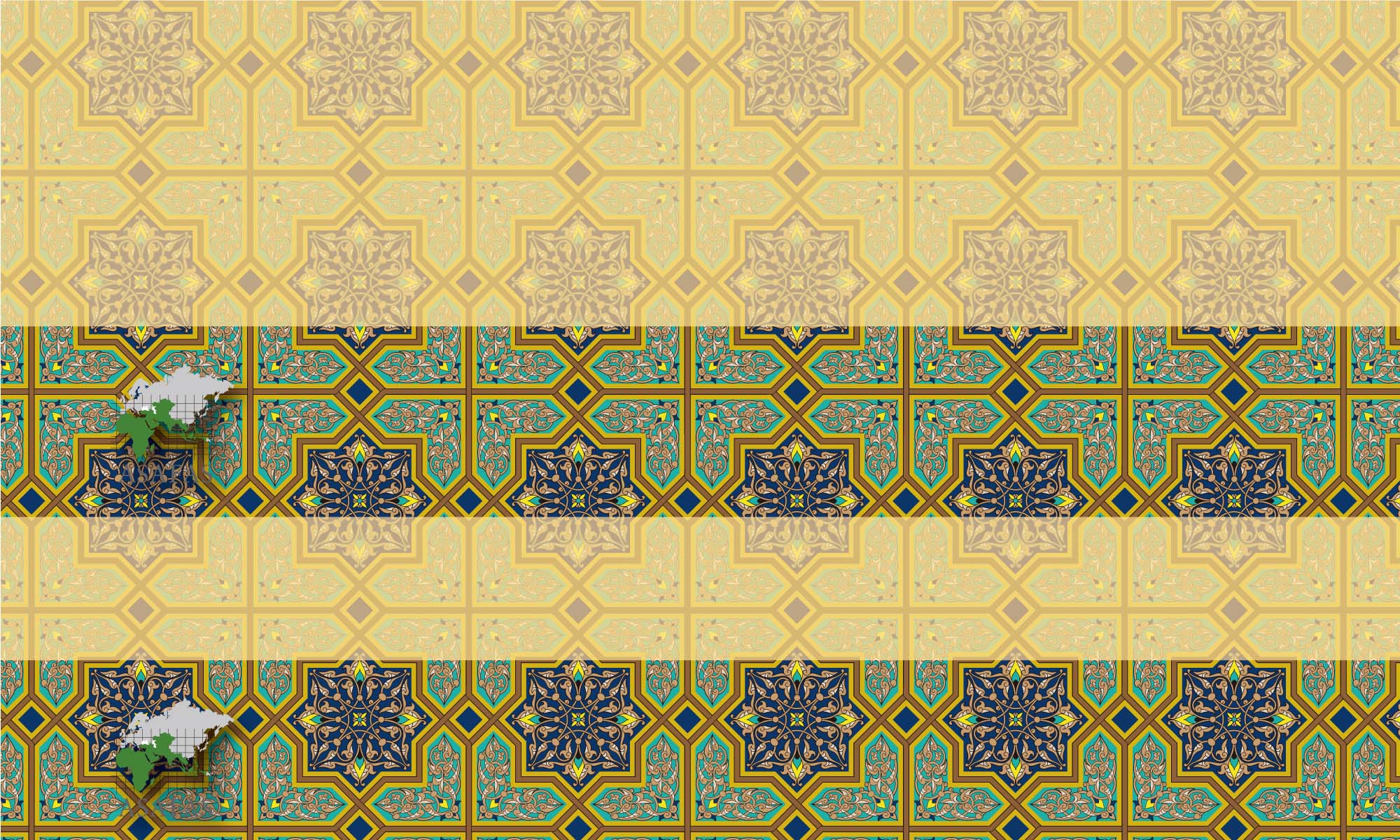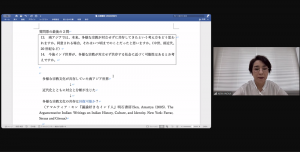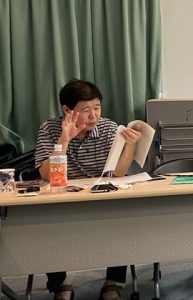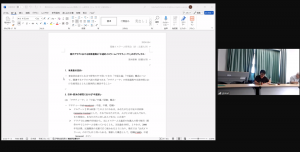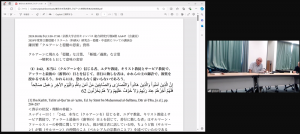科研基盤A「非アラブにおける穏健イスラームの研究-インドネシア・パキスタン・トルコの事例から」 2025年度第2回研究会(「穏健イスラーム」研究会)
【日時】9月6日(土)14:00–18:00
【場所】上智大学総合グローバル学部小会議室(2号館6階2-615a)
【報告1】井上あえか(就実大学)、山根聡(大阪大学) 「パキスタンにおける穏健イスラームへの意識-2024年8月のアンケート結果から」
今回の報告では、2024年8月末にパキスタンの首都イスラーマーバードとラーホールで実施したパキスタン社会における穏健派に対する意識調査の結果を受けて、その傾向について報告を行った。調査は無記名の記入式で実施し、大学生を中心に10代後半から70代までのパキスタン人を対象に行った。大学や研究機関で実施したために回答者89名のうち70人が20代と30代と若い世代が占めていた。報告ではまず、パキスタン社会が建国以来現在までイスラーム化と世俗化の間を行き来しており、保守的か世俗的かという選択肢に対する関心が低いがために、「穏健派」や「中道派」について知らないと答えた人数が57人と多く出たことが特徴的であった。ただ、アンケート実施に先立って穏健派や中道派に関する説明を行ったことや、聖者廟への襲撃に対する批判的な姿勢が多かったこともあって、穏健派や中道派そのものを支持する意見は多かった。その印象は「中立的」や「バランスが取れている」といった印象を答える傾向が多かった。また、近年の聖者廟襲撃に対しては強く批判する声が高く、聖者廟に対して否定的な少数意見(11件)があるとはいえ、襲撃を肯定する意見はなかった。
また聖者廟を訪問する場合のその目的は、その多くが祈り(ドゥアー)のためという回答が多かった一方で「願いはアッラーに願うもの」という意見も少数ながらみられた。また、聖者に頼るという姿勢は少なく、「両親の健康を願う」といった程度の願いや、単なる訪問や観光といった回答が多くみられた。スーフィーの言動については、その言葉に真実があるという回答が多かった。
また、スーフィーの歌(カーフィーやカウワーリー)では誰の作品が好きかという質問には聖者名よりも、カウワールのヌスラット・ファテ・アリー・ハーンの名前を回答する場合がほとんどで、カウワールの歌謡が人々に浸透している状況が見られた。
また、liberal、moderate、centralの印象については、パキスタンの歴史からもリベラルを非イスラーム的、もしくは「恥知らず」といった世俗的な姿勢と捉えることが多かった。将来のパキスタン社会については、半数近くの37名が穏健的な環境を望んでいるものの、14名はより宗教的であるべきだと答える者があって、特に10代後半の回答者を占めていた。これについては、「イムラーン世代」ともいえる、これまでの政治体制を否定し、汚職を追放し、社会的公正を掲げつつ、イスラーム的価値観を強調しているイムラーン・ハーン前首相を支持する若い世代に反映しているといえよう。
南アジアにおける宗教的共存は印パ独立以前にあったという意見もあったが、今後の共存の可能性については、共存を求める声が多数存在するのに対し、「共存は望ましいが、政治的な緊張関係が解消されない限り現実的ではない」という意見もあった。
アンケートに対し、回答者が大変真摯に答えてくださったことから、この時代の学生らの意識が反映された大変興味深い結果となり、質疑においてもアラブ世界やインドネシアでの状況と比較するなど、大変活発な意見交換がなされた。
【報告2】新井和広(慶応義塾大学)「インドネシアにおけるアラブ系学識者クライシュ・シハーブとワサティーヤ・穏健イスラーム」 本報告ではインドネシアにおけるアラブ系学識者、クライシュ・シハーブのワサティーヤ・穏健イスラームの概念を彼の著作『ワサティーヤ』をもとに検討した。クライシュ・シハーブはインドネシア生まれのアラブ(ハドラミー)であり、アズハル大学に留学してクルアーン学で博士号を取得した人物で、インドネシアの宗教界における有力者のひとりである。その一方で本人は否定しているもののシーア派であると非難されてきた。
著書『ワサティーヤ』においてはクルアーン、ハディース、古典的なテキストからワサティーヤ、または穏健に関して社会、政治、経済などと関連づけてスンナ派における典型的な論を展開していると考えられる。特に著者が強調しているのは穏健、またはワサトであるためには常に状況を把握し、考え、それぞれの実情に合わせて態度を調整する必要があるという点である。換言すればワサティーヤは決して受け身で優柔不断というわけではなく、能動的態度である。
本書の出版のきっかけとなったのは宗教省主催の行事で行った穏健に関する講演だが、本書の中身にはインドネシアにおける「モデラシ・ブルアガマ」ほか、政府の政策やイスラームに関する議論については全くと言って良いほど触れられていない。これは著者が古典的な学問の専門家であることに加え、現代インドネシアにおける論争に関わらないようにするという意図を読み取ることができる。
いずれにしてもワサティーヤについての古典的な議論をある程度網羅しているので、インドネシアにおける今後の穏健イスラームに関する研究においても事あるごとに参照すべき文献だと言える。