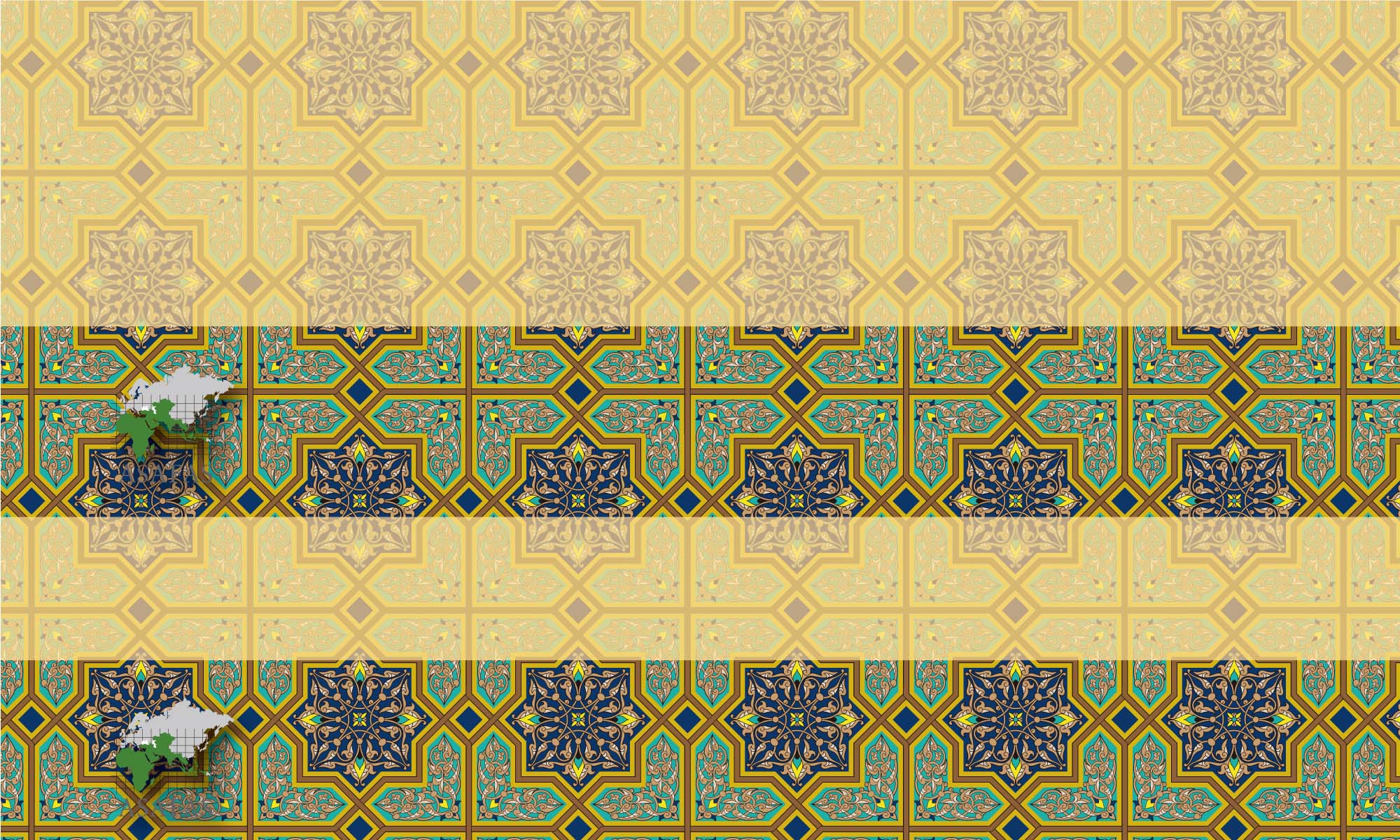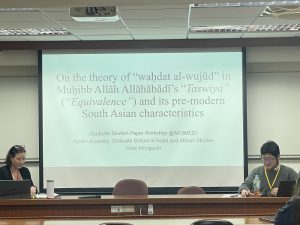地中海研究機関アジア連盟(Asian Federation of Mediterranean Studies Institutes, AFOMEDI)第4回国際会議“Spaces of Familiarity, Spaces of Difference in the Mediterranean” 報告書
棚橋由賀里・本間流星・森口遥平
第4回目となるAFOMEDI国際会議、“Spaces of Familiarity, Spaces of Difference in the Mediterranean”(地中海における親しみの空間、差異の空間)が、台湾国立の学術研究機関である中央研究院歴史語言研究所にて開催された。コロナ禍以降初となる対面開催であり、3月18日(月)と19日(火)の2日間で計17のパネル・セッションが組まれ、歴史学・考古学・文学・人類学・文献学といった様々な観点から研究発表が行われた。これまでは台湾・韓国・日本の研究機関が中心となってきたが、今回は欧米、中東・北アフリカ、東南アジア、オセアニアと幅広い地域の研究者が参加し、非常に活気に満ちた会議となった。
参加学生の報告書は以下のとおりである。
棚橋由賀里
報告者は、ポルトガルの侵攻に苦しんだ15–16世紀のモロッコを研究対象としているため、中世・近世の地中海における外交、戦争、海賊行為などを扱ったパネルに関心を持った。特に以下の発表が興味深かった。1日目第2セッション“The Limits of Familiarity in Sixteenth-Century Cross-Confessional Mediterranean Diplomacy”におけるRubén González Cuerva氏(スペイン国立研究評議会)の発表“Familiarity beyond Religion? Patterns of Negotiated Exchanges in Habsburg-Hafsi Diplomacy (1535-1573)”は、オスマン帝国に対抗してスペイン・ハプスブルク家とチュニジアのハフス朝が結んだ同盟関係に関して、主に贈り物・書簡の交換や翻訳活動といった形式の交流に光を当てたものであった。両者の緊張関係が、信仰する宗教によってではなく、外交において文書と口頭の会話のいずれを重視するかという様式の違いによって露わになった点が興味深かったとともに、宗教以外の対立軸を考慮する必要性を再認識した。また同日第5セッション“Violence and the Sea in the Medieval Mediterranean”におけるTravis Bruce氏(マギル大学)の“Medieval Maritime Violence and Mediterranean Spiritual Economy”は、中世地中海の海事における受難、すなわち海戦・海賊行為によって略奪や身体拘束を扱ったものである。暴力を被る経験は、キリスト教徒・ムスリム双方にとって、敬虔な信徒が信仰心によって苦難を耐え忍ぶ物語や、神が信徒たちを拘束や虐待から救うために介入する物語を生み出したほか、富裕な者にとっては自らの富を身代金の支払いすなわち同胞救済に擲つという一種の浄化行為を行う機会となったという。苦難の経験を宗教的な文脈でプラスに転換するという現象に関して、“spiritual economy”あるいは“spiritual capital”という枠組みを用いた研究は、本邦の心性史研究では菅見の限り出会ったことがなく、新鮮であった。
報告者は、2日目の第13セッション“Islamic Spaces and Colonial Resistance”において“Social Reform in the 15-16th Centuries Morocco Tackled by the Sufis of al-Ṭarīqa al-Jazūlīya”というタイトルで発表をおこなった。内容としては、ポルトガルの侵攻に苦しむ15–16世紀モロッコにおいて、これまで「スーフィー教団」という枠組みで語られてきたタリーカ・ジャズーリーヤという道統のスーフィーたちの社会改革について、宗教教育・政治参加・慈善活動といったトピックを挙げてその個別性・多様性を論じたものである。コメンテーターのTravis Bruce氏(マギル大学)からは、“Colonial Resistance”というテーマと関連した議論を求められた。報告者は、外部からの征服に対する反応として宗教的な純粋さを取り戻そうとする機運が生じること自体には時代を超えた普遍性があるとしつつも、国民国家の概念が存在しなかった前近代モロッコにおいて、集団的な抵抗を想起させる“Colonial Resistance”という語を安易に当てはめることには慎重でありたいと述べた。
(以上文責:棚橋由賀里)
報告者が特に関心を抱いたのは、1日目の第6セッション“Political Cultures and the Shaping of Spaces”におけるPeter Kitlas氏(ベイルート・アメリカン大学)の発表“Scribal Spaces and Diplomatic Knowledge Production in the Eighteenth-Century Muslim Mediterranean”である。本発表は、18世紀の地中海地域におけるムスリム外交官らの知的・文化的コンテクストを、当時の北アフリカとオスマン帝国に焦点を当てて考察するというものであり、そこでは前近代から近代の転換点という時代の中でムスリム個々人が地中海地域の外交において果たした役割が示された。地中海地域のムスリム外交官らの知的営為を「書記文化(scribal culture)」という枠組みで論じた本発表は、ムスリム地域の外交史研究のみならず、思想・文化研究への幅広い視点をも有していた。
報告者は、2日目の第13セッション“Islamic Spaces and Colonial Resistance”において、“Ashraf ‘Alī Thānavī and Sufi Metaphysics: The Modern Development of the School of Ibn ‘Arabī in South Asia”と題した発表を行い、これまで看過されてきた近代南アジアのイブン・アラビー学派に関して、デーオバンド派の学者且つチシュティー派のスーフィーであったアシュラフ・アリー・ターナヴィー(d. 1943)の著作群に着目して論じた。コメンテーターのTravis Bruce氏(マギル大学)からは、イギリス植民地期という政治的・社会的文脈により関連付けた議論を求められた。それに対して報告者は、ターナヴィーのスーフィー形而上学と植民地期南アジアの政治・社会の密接な関わりを現時点では見出せていないと断りを入れた上で、ムスリム連盟のパキスタン建国運動における晩年のターナヴィーの関与について説明した。
「地中海地域における親近性/相違性の空間」が大きなテーマとして掲げられた今大会では、キリスト教とイスラームを中心に多くの異なる宗教文化が歴史的に交差してきた当該地域において、それら諸宗教が如何なる仕方で政治的・社会的・知的に関わり合い、対立・調和を繰り返してきたのかという点に着目した発表が多かったように思われる。また、地中海には直接的に面していない東・東南アジアを含む広範な諸地域に関しても頻繁に論じられ、「地中海地域」という概念自体に対する再検討の試みが見られた点は、今後の研究の裾野を拡げるという意味でも大きな意義があったと考える。
(以上文責:本間流星)
本学会のテーマは地中海の研究であったが、AFOMEDI運営メンバーである東長靖先生のご厚意で発表の機会をいただいた。私の発表は大会2日目に「大学院生ワークショップ」と題されたセクション内でおこなわれた。10分の発表後、コメンテーターのフィードバック、聴講者との質疑応答というスタイルだった。報告者は、予備論文で論じた前近代南アジアのイスラーム神秘主義思想に関して発表した。北アフリカのイスラーム法学を専攻するコメンテーターとのディスカッション、多様な研究関心を持つ聴講者との質疑応答は、博士予備論文を書き終え、博士論文に向けて学問的関心を広げるという点で有意義だった。本学会は、東アジアや東南アジア、ヨーロッパやアメリカからの60名ほどの参加者がいたが、様々な文化的背景を持ち、多様な研究をおこなう教授や院生と学会中を通じて交流を楽しむことができた。今後、共同研究などに繋げていきたいと思う。また、1日目のTeofilo Ruiz氏(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)によるキーノートスピーチ“In Search of Deliverance: Lived Experiences of Mediterranean Space in the Past and Present”では、同氏の人生が語られたが、出身地のキューバの社会混乱など様々な逆境に置かれつつも、研究し続けたという内容に感銘を受けた。
以下は、報告者が中央研究院に滞在するなかで得た所感である。まず指摘したいのは、構内で多くのインド人研究者を目にしたことである。先日、京大の学内広報誌で「日本および京都大学はインド人学生・研究者の招へいを進めている」と読んだが、自国外の優秀な研究者や学生の獲得競争がアジアでも本格化していると感じた。このことは、前回まではアジアからの参加者のみであったのに対して、今回は世界中からの参加者がいたことと無関係ではないはずだ。また、もう一点報告者が注目したこととして、会場補佐を担当していた学生の英語力の高さが挙げられる。会場内での英語対応や学会後の懇親会での参加者との会話などを耳にしただけだが、いずれも円滑におこなっていた。このことも台湾の大学が国際化に力を入れていることの傍証だと思われる。
(以上文責:森口遥平)