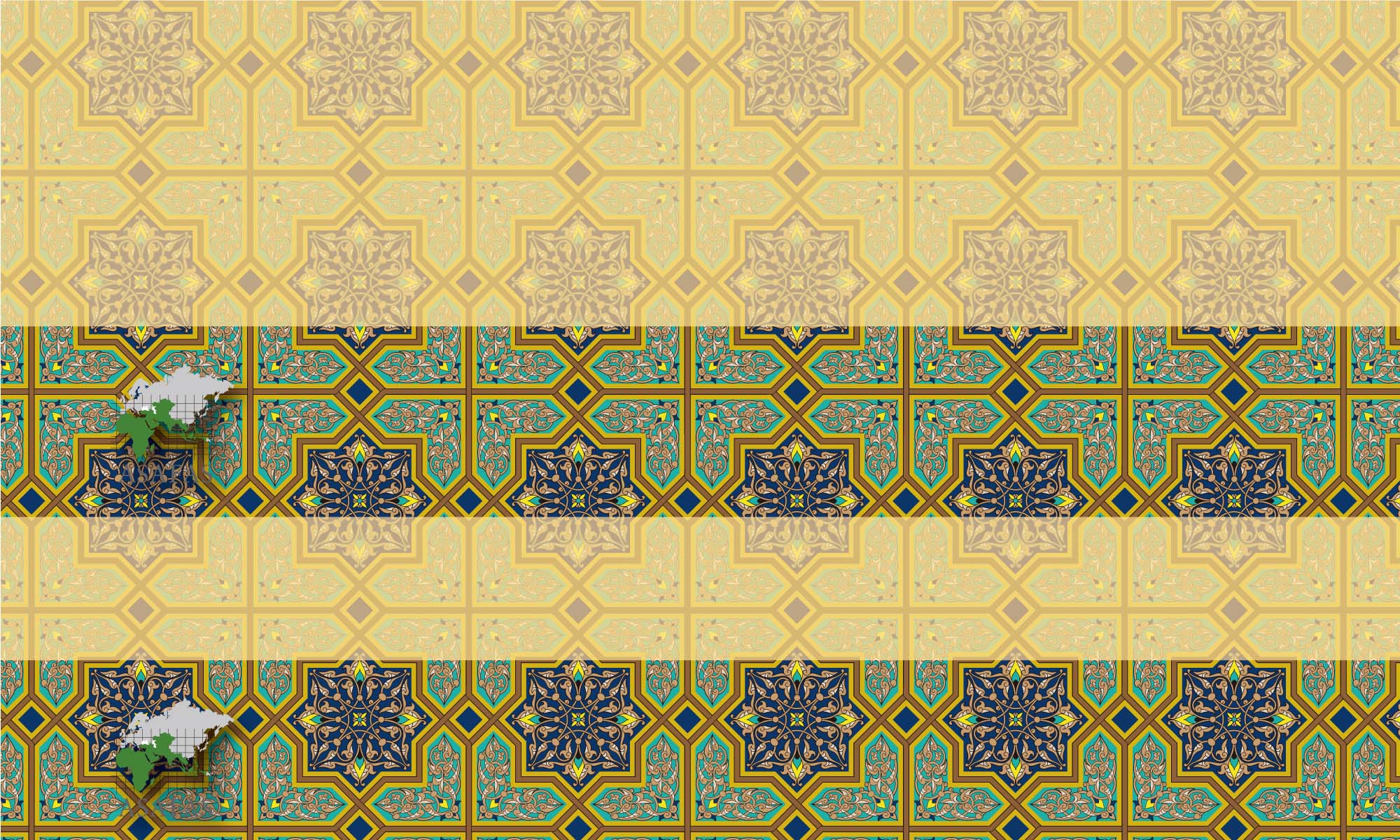【日時】2020年2月17日(月)10:00−17:30
【場所】Theater, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
【プログラム】
Keynote Speech 1: TONAGA Yasushi (Kyoto University) “Wisdom of Coexistence according to Sufism”
Keynote Speech 2: Oman FATHURAHMAN (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) “Female Indonesian Sufis: Shattariyah Murids in the 18th and 19th Centuries in Java”
SESSION 1 (Chair: FUTATSUYAMA Tatsuro)
TANAHASHI Yukari (Kyoto University) “The Theological Thought of Muḥammad ibn Sulaymān al-Jazūlī”
Arif ZAMHARI (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) “Innovation in Indonesia’s Sufi Tradition: Urban Majlis Zikir dan Salawat”
Bambang IRAWAN (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) “Tasawuf and Radicalism”
SESSION 2(Chair: Agus RIFA’)
Yoyo HAMBALI (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) “Ibn ‘Arabi on Relation of Sshari’a and Haqiqa”
MATSUDA Kazunori (Kyoto University) “Sana’ullah Amritsari and his Urdu Proses”
M. NIDA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) “Kyai Hasan Maolani; Tarekat and Collonialism”
【共催】
Kenan Rifai Center for Sufi Studies (KR),
Center for Islamic Area Studies (KIAS)
Graduate School of Asian African Area Studies (ASAFAS)
Jakarta Liaison Office of Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
Graduate School of UIN